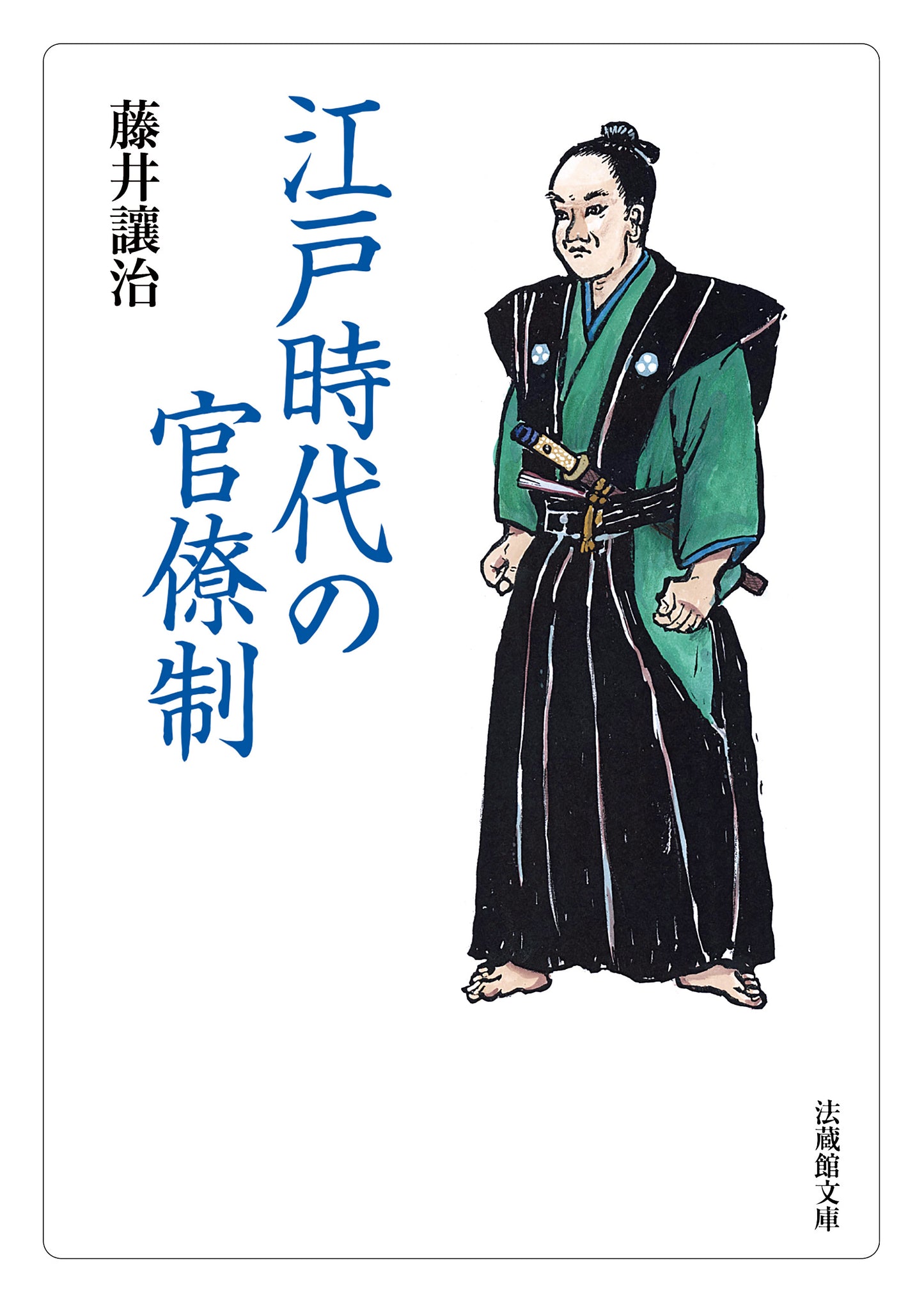ちえうみ
江戸時代の官僚制
江戸時代の官僚制
受取状況を読み込めませんでした
一次史料にもとづく堅実な分析と考察から、幕藩官僚=「職」の創出過程とその実態・特質を解明。幕藩官僚制の内実を、明瞭かつコンパクトに論じた日本近世史の快著。
【目次】
凡例
読者へ
Ⅰ章 大久保長安と大岡忠相
1 大久保長安
長安の出自/直轄領支配/長安と金山/知行割/奉行長安/宿駅の整備/検地/信濃・越後支配と松平忠輝/駿府年寄としての長安/各地に現れる長安
2 大岡忠相
出自と家柄/一族の危機/家督相続と書院番就職/徒頭・使番・目付/山田奉行・普請奉行/町奉行忠相/寺社奉行忠相とその日常/忠相と長安
Ⅱ章 「人」から「職」へ
1 出頭人政治の時代
天下人・家康と秀忠/本多正純/所司代板倉勝重/小堀政一/出頭人政治の矛盾/秀忠大御所時代の幕政運営/本丸西丸年寄連署奉書
2 代替りの軋轢
西丸年寄制の解体/旧年寄衆の排除/稲葉正勝の取り立て/惣目付の監察/松平正綱・伊丹康勝の勘当/「六人衆」の成立
Ⅲ章 「職」の形成とその特質
1 「職」の形成
三つの法度/三つの法度の意味/松平信綱らの奉書加判/将軍諸職直轄制/将軍諸職直轄制の麻痺/老中制の確立
2 「職」形成の諸相
若年寄/寺社奉行/町奉行/勘定奉行/所司代と京都町奉行/表象としての役所
3 「職」と武士身分
身分・階層と「職」/「職」と朝廷官位/「御為第一」の原則
4 幕藩官僚制の運用と人的再生産
合議制と月番制/合議制・月番制の限定化/昇進の世界/役料制の導入/家禄を減じる世減制
Ⅳ章 十七世紀中葉の幕府官僚たち
1 寛文四年の大名・旗本
寛文四年という年/『寛政重修諸家譜』/幕府家臣団の概要/寛文四年の大名/寛文四年の旗本/旗本の知行・俸禄
2 寛文四年「職」の世界
弘化二年と寛文四年の職制/寛文四年の主要な職/人員の変化/知行高と職
3 昇進の諸相
大番の昇進/書院番の昇進/小姓組の昇進/三番の比較/新番・小十人の昇進/代官・蔵奉行・勘定の昇進/納戸・小納戸の昇進/桐間番の昇進/徒頭・使番・目付の昇進/留守居番・先鉄砲頭の昇進/遠国奉行の昇進/作事奉行・普請奉行の昇進/勘定奉行・町奉行・大目付の昇進/留守居・側・定火消の昇進/昇進ルートの概要
4 家格の上昇
大名への上昇/昇進による大名化/旗本内での家格の上昇/大番筋と両番筋/御家人から旗本へ
終章―まとめにかえて―
「職」の形成/幕藩官僚制の特質/寛文四年の世界
参考文献一覧
あとがき
文庫版あとがき
江戸幕府職名索引
藤井讓治・著
1947年福井県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。京都大学大学院文学研究科教授を経て、現在、同大学名誉教授・石川県立歴史博物館館長。専攻は日本近世史。著書に、『江戸幕府老中制形成過程の研究』(校倉書房)、『幕藩領主の権力構造』『戦国乱世から太平の世へ』『近世初期政治史研究』(以上、岩波書店)、『徳川将軍家領知宛行制の研究』(思文閣出版)、『徳川家光』『徳川家康』(以上、吉川弘文館)、『天皇と天下人』『江戸開幕』(以上、講談社)など多数。
ISBN:978-4831826527
出版社:法藏館
発売日:2023/9/8
Share