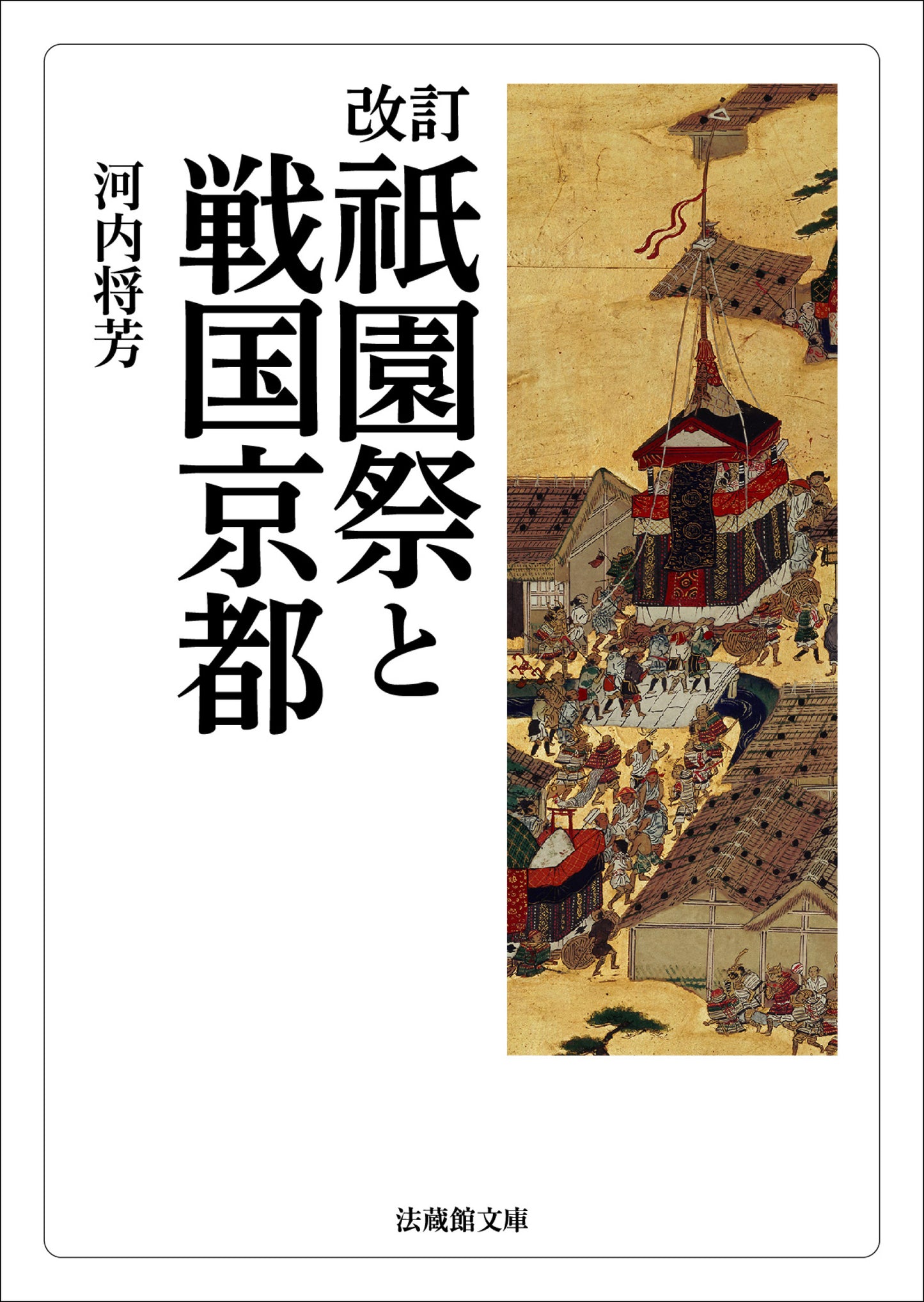ちえうみ
改訂 祇園祭と戦国京都
改訂 祇園祭と戦国京都
受取状況を読み込めませんでした
創作物を通じて祇園祭に託された「権力に抵抗する民衆の祭」イメージは、はたして実態に合うものなのか。創作物の題材である戦国期の祇園祭にスポットを当て、イメージと史実の比較から中世都市祭礼・祇園祭のリアルに迫る。
?
【目次】
はじめに
現在の山鉾巡行/山鉾巡行の道筋/戦後におこった大きな変化/解体される山鉾と疫神遷却/現在の神輿渡御/神輿渡御と御旅所/冬の祇園祭/戦国時代の祇園祭に対するイメージ
第一章 イメージとしての祇園祭
1 紙芝居「祇園祭」
『祇園祭』(東京大学出版会)の刊行/紙芝居「祇園祭」の製作/国民的歴史学運動と祇園祭/紙芝居「祇園祭」のストーリー/紙芝居に対する反応
2 小説『祇園祭』と映画『祇園祭』
数奇な運命/映画『祇園祭』のストーリー/巨大オープンセットと有名俳優/かたちづくられてきたイメージ
第二章 天文二年の祇園祭
1 天文元年~二年六月の政治状況
天下将軍御二人/一向一揆と法華一揆/都市と都市の戦い/一向一揆との攻防/大坂本願寺との戦い/近づく式日
2 天文二年の祇園祭
祭礼執行の主導権/将軍義晴の意向/山門として申し入る/延暦寺大衆の圧力/神事これなくとも、山ホコ渡したき/天文二年の山鉾と町/祭礼の追行/七日山鉾と十四日山々/都市民衆と幕府と延暦寺大衆/権門体制と王法仏法相依/神仏習合と寺社
第三章 室町幕府にとっての祇園祭
1 祇園祭の再興
再興までの道程/三基の神輿と御旅所/明応九年の再興/幕府の強い意向/再興された祇園会/山鉾の数/神輿渡御
2 幕府と祇園祭
将軍による見物/足利義澄と祇園会/細川政元と祇園会/三三年と恠異/『祇園会山鉾事』/侍所開闔松田頼亮/頼亮と鬮取り/二度の祇園会/大永二年の祇園会/再現された祇園会御成/山鉾の巡行ルート/戦国時代の将軍と祇園会
第四章 延暦寺大衆にとっての祇園祭
1 日吉社の祭礼と祇園祭
延暦寺末寺・日吉社末社としての祇園社/日吉祭、日吉小五月会、祇園会、北野祭/祭礼間の順序/恠異と延暦寺大衆/馬上一衆・合力神人制/馬上役/馬上役と山鉾
2 延暦寺大衆と祇園祭
馬上役と御旅所神主/少将井御旅所神主職と禅住坊/転換点としての文安六年/応仁・文明の乱から戦国時代へ/枠組みとしての馬上役/有名無実化する馬上役/迷走する式日/元亀二年以降に安定する式日/幕府と延暦寺大衆と祇園会
第五章 神輿と山鉾の祇園祭
1 神輿渡御
神幸路/描かれた御旅所/供奉した人びと/犬神人・四座の衆・師子の衆/大宮駕輿丁/今宮神人と魚物商売/魚物商売をめぐる攻防/犀鉾神人と堀川神人/少将井駒頭/御霊神子/戦国時代の神輿渡御とにない手
2 山鉾巡行
神輿渡御の停止/山鉾巡行の停止/山鉾のにない手/大舎人と鵲鉾/すがたを消した鵲鉾/地域に密着した山鉾へ/天文法華の乱後の復興/四条綾小路町人らの申状/訴えの内容/祇園会出銭/史料にみられる祇園会出銭/狂言『鬮罪人』と山の相談/鬮取り/祇園の会の頭/頭屋と神事
おわりに
「神役」「所役」/「所役」と名誉/祇園会と「町衆」と「町」/戦国時代の後
関連略年表/図版出典一覧/あとがき/文庫版あとがき
?
河内将芳・著
1963年大阪市に生まれる。1987年京都府立大学文学部卒業。1999年京都大学大学院博士課程修了。京都大学博士(人間・環境学)。1987年甲南中学・高等学校教諭、2001年京都造形芸術大学芸術学部専任講師、2003年同助教授、2005年奈良大学文学部助教授、2007年同准教授、2010年同教授、現在に至る。主な著書に、『中世京都の民衆と社会』(思文閣出版、2000年)、『中世京都の都市と宗教』(思文閣出版、2006年)、『祇園祭の中世――室町・戦国期を中心に――』(思文閣出版、2012年)、『絵画史料が語る祇園祭――戦国期祇園祭礼の様相――』(淡交社、2015年)、『戦国仏教と京都――法華宗・日蓮宗を中心に――』(法藏館、2019年)、『室町時代の祇園祭』(法藏館、2020年)などがある。
?
ISBN:978-4831826244
出版社:法藏館
発売日:2021/7/9
Share